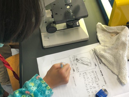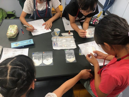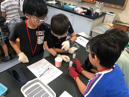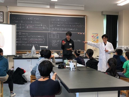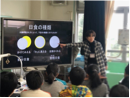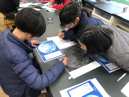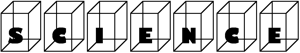
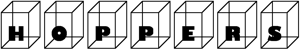
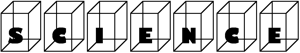
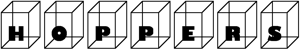

2019年度
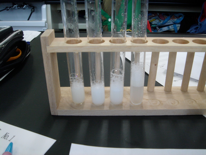
4月 水中の微生物の観察
5月 金属を溶かして
キーホルダーを作ろう
6月 犯人を探せ 〜生物を使った科学捜査〜
7月 フライドチキンから骨を学ぼう
9月 ドライアイスで遊ぼう
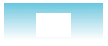

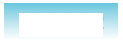

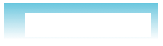





10月 はんだごてを使った電子工作
11月 暑くなる地球と私たち
12月 部分日食を観察しよう
2月 フィールドワーク
3月 ガラスの化学





第174回 水中の小さな生き物たちの観察
2019年4月27日土曜日
顕微鏡の使い方をマスターして、水中の小さな生き物たちを
観察しました。
ミジンコ、ボルボックス、ゾウリムシ、ミドリムシ・・・
他にも、タイリクミジンコ、ミカヅキモ、イカダモもみられるかも





第175回 金属を溶かしてキーホルダーを作ろう
2019年5月25日土曜日
金属のスズ合金「ピューター」は250度で溶けます。
溶かした金属を型に流し込み、世界で1つのキーホルダーを作りました。
金属をどろどろに溶かして型に流し込む作り方は、鋳造(ちゅうぞう)と言います。ほかにも鍛造、ブレス加工のことを学びました。
金属をみがく作業は、根気のいる作業でした。


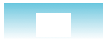

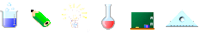

第176回 犯人を探せ! 〜生き物を活用した科学捜査〜
2019年6月29日土曜日
生物を活用し、犯人をさがす!。考えながらの科学捜査体験授業!
とある会場で事件がおきました。そこには「謎の粉」が残され、粉の正体
を4つの粉から化学反応から分析していきます。
グループ毎で話し合い、グループで犯人を突き止めていきます。
みんなよく考え、意見を出し合いながら取り組んだSTEM(Science Technology Engineering Maths) 体験教室でした。
第177回 フライドチキンから骨を学ぼう
2019年7月13日土曜日
フライドチキンからニワトリという動物について、また、動物の骨や骨格
について学びました。
いつも食べているチキン。どの部位だったのか? どの骨の部分?
そして、人間との骨のつくりの違いなどを学びました。
「いただきます」の言葉にこめられた意味も考えました。
第178回 ドライアイスで遊ぼう
2019年9月21日土曜日
ドライアイスを使って実験をしました。机の上をすべらせたり、スプーン
から音をだしたり、袋の中に入れたら・・・
それから、フィルムケースロケットを作って飛ばす!
他にも、市販のジュースを使って、炭酸ジュースも
作って、試飲しました。
第179回 はんだごてを使った電子工作
2019年10月19日土曜日
はんだごてを使って、電気回路を作りました。 (内容は、昨年と同様)
はんだの使い方と説明をうけたら、まず回路図をもとに作る。
とにかく、やってみる。 キット製品ではないので、自由に作る。
できた人は、青色LEDや違う抵抗を使って、他のことにも挑戦。
なんと、今年は色を変えてみたり、スイッチで回路を工夫してみたりと
いろいろな作品をみることができました!すごい!
第180回 暑くなる地球と私たち
〜サイエンスコミュニケーションを始めよう!〜
2019年11月16日土曜日
地球温暖化という言葉をよく聞きます。実験をとおして地球温暖化のことを学びました。電気をつくること、発電のこと、二酸化炭素のこと。
温暖化にならないように考えるゲームを2つ1組のグループで考え、何回かディベートをしながら、対策や答えをまとめていきました。
興味深い実験& 授業でした。
第181回 部分日食を観察しよう
2019年12月26日木曜日
太陽が欠けて行く様子を観察する予定でしたが、あいにく天気は曇り。
残念ながら当日は観察できませんでしたが、日食のしくみを学びました。
観察できない時のため、先生が「月のクレーター探し」のプログラムを
用意してくださいました。
月のクレーターや山や谷には、1つ1つステキな名前がついています。(2020年6月21日夏至にも部分日食があります。当日配布した日食グラスで、ぜひ観察してください。)
第182回 フィールドワーク
2020年2月8日土曜日
井の頭公園に冬になったらやってくる鳥、公園にいつもいる鳥の観察をしました。カモ科だけでも冬鳥のオカヨシガモ、オナガガモ、キンクロハジロ、コガモ、ハシビロガモ、マガモ、留鳥のカルガモを観察。
その他、カワウ、ゴイサギ、アオサギ、バン、ハクセキレイなどなど・・
2時間、いろいろな種類の冬鳥を近くでみることができました。
第183回 ガラスの化学 トンボ玉を作ろう
2020年3月14日土曜日
新型コロナウィルス拡大のため、中止